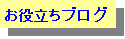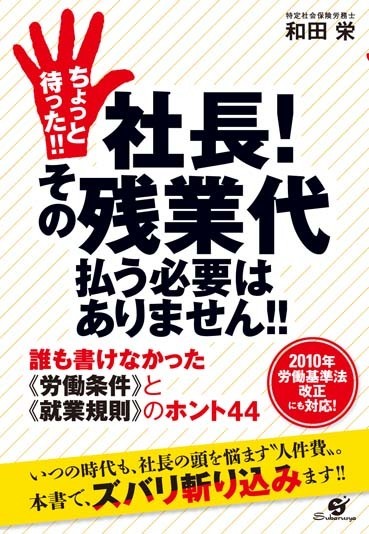質問1「祖母が亡くなったのですが、慶弔休暇はいただけますか?」
質問2「昨日の欠勤を年次有給休暇に振り替えてもいいですか?」
質問3「裁判員で休んだ場合は有給になりますか?」
質問4「電車の遅れで遅刻した場合も給与は引かれてしまいますか?」
質問5「育児休業期間は勤続年数に通算されますか?」
社員からこんな質問を受けたとき、社長は明確に答えられますか?
どの質問も法律の決まりはありません。
したがって、会社が自由に決めることができます。
さて、法律で決められていれば答えは簡単ですが、会社が決めていいとなると意外に迷います。
●会社の負担は?
●社員の興味や期待は?
●世間相場は?
●企業理念との整合性は?
いろいろなことを考えなければならず、相当頭を悩ませます。
これをその都度検討していたのでは、時間もかかるうえ場当たり的にもなりかねず、社員の不審を買う危険性があります。
そこで必要になるのが就業規則です。
就業規則は会社のルールを定めたものですが、より具体的に詳しく定めることでマニュアルとしても使うことができます。
例えば、次のような事項。
「年次有給休暇を取得する場合は、1週間前までに所属長に所定の書面で届け出ること」
これはルールですが、手続きマニュアルとしても使えます。
年次有給休暇をとるためには、1週間前までに所属長に休暇届を提出すればいいということがわかります。
これがあれば、社員から「年次有給休暇をとるためにはどうしたらいいんですか?」なんて質問はなくなるわけです。
「制度や手続きは就業規則を見てくれ!」
と言えるようになれば、社長は楽ですよね。
実は、冒頭の質問は私がよく相談される事項なのですが、就業規則がないかあるいはあってもあいまいで判断が付かないといった場合によくあるケースです。
では、それぞれの質問について、詳しく見てみましょう。
質問1「祖母が亡くなったのですが、慶弔休暇はいただけますか?」
だいたいの慶弔休暇は「父母」「子」「兄弟姉妹」については決められていますが、「祖父母」「孫」となるとあいまいなケースがよくあります。
というのは、「祖父母」となると、「同居」か「別居」かで大きな違いがあり、さらに「配偶者の祖父母」についてはどうかといった複雑さのため、あいまいな規定になりやすいのです。
「同居の祖父母」のつもりで規定していても、「同居」という文言が漏れたりすると、「別居の祖父母」が亡くなった場合に悩むことになります。
きちんと区別して規定しておく必要があります。
質問2「昨日の欠勤を年次有給休暇に振り替えてもいいですか?」
病欠のときによくあるケースです。
予定して休むわけではないので、事前に年次有給休暇を申請するわけにはいきません。
やむなく事後申請するわけですが、これを認めるかどうかは会社の自由です。
もちろん自由といっても人によって認めたり認めなかったりを自由に決められるということではなく、認める制度にするか認めない制度にするかを決められるという意味です。
実際には認める会社が多いようですが、認めるのであればその旨規定しておくべきです。
規定がなければ認めないということになりますが、マニュアルとして使いたいのであれば認めない旨規定しておいた方がよいでしょう。
なお、本人の申請があって初めて年次有給休暇に振り替えられるので、会社が勝手に振り替えることはできません。
そういう意味では、振替申請をできる期間を決めておいた方がよいでしょう。
質問3「裁判員で休んだ場合は有給になりますか?」
いよいよ平成21年5月から裁判員制度が始まりました。
まだ社員の中で選ばれた人はいないかもしれませんが、これから先、確率的には選ばれる可能性は十分あります。
さて、裁判員に選ばれた場合、会社を休んででも参加しなければならないわけですが、このとき有給なのか無給なのかという問題があります。
本人にしてみれば、休みたくて休むわけではないので給与は補償してほしいところでしょうが、会社にしてみれば、国の制度のためになぜ会社が給与を負担しなければならないのかというところでしょう。
法律では、会社に給与の支払いを義務づけてはいないので、有給にする必要はありません。
本人には、国から最高1万円の日当が支払われます。
でも、日給換算するとたいていの人は1万円を超えるので、無給だと日当をもらっても赤字なんですよね。
そこで、有給扱いとしておいて、日当相当額は差し引くという手もあります。
会社が差額を負担することになりますが、実際には年次有給休暇をとって、給与と日当両方をもらうというケースがほとんどだと思いますのでほとんど問題はありません。
それにしても、裁判制度始まって以来の大改革だというのに、日当があまりにも低いと感じるのは私だけでしょうか...。
質問4「電車の遅れで遅刻した場合も給与は引かれてしまいますか?」
理由はどうあれ、遅刻は遅刻なので、ノーワークノーペイの原則で給与を支払う必要はありません。
しかし、本人は悪くないという理由で遅刻扱いにしない会社は多いようです。
この場合、証明書を提出させるのが一般的です。
問題は、渋滞による遅刻です。
理屈は電車の遅れと同じですが、証明ができません。
それでもやはり本人を信じて遅刻扱いにしない会社は多いようです。
でも、これって本当に公平かというと微妙なところです。
同じ経路で通勤する場合でも遅刻しない社員がいます。
いつも余裕をもって早めに家を出ている社員です。
ちょっと電車が遅れたり渋滞したくらいで遅刻する社員は、いつもぎりぎりに出勤している社員です。
いくら不可抗力だからといって、遅刻扱いにしないというのはいかがなものでしょうか。
遅刻しないで出勤してきている社員に対して不公平ではないでしょうか。
せめて、「30分までは遅刻扱いにしない」などの歯止めは必要だと思います。
質問5「育児休業期間は勤続年数に通算されますか?」
これは主に退職金に関係した事項です。
退職金の計算には通常勤続年数が関係するので、約1年間の育児休業期間が通算されるのかされないのかは社員にとって大きな問題です。
退職金自体あってもなくてもいいものなので、その計算方法も自由です。
退職金を勤務期間中の功労と見れば、育児休業中は会社に貢献していないので、退職金の計算期間からはずすというのも根拠があります。
一方、出産育児に関しては公平性を保つため、退職金に差を付けないように計算期間に通算するという社会性を意識した考えもあります。
これはよい悪いはなく、会社の負担も小さくないことですし、社長の考え方次第といったところでしょう。
他に「産前産後休業」や「介護休業」も同様のことがいえます。
以上、5つのケースを見てきましたが、
実務で疑問に思ったり迷ったりするケースはある程度想定されます。
そのようなことは、あらかじめ就業規則で具体的に規定しておきましょう!
「そうはいってもどうすれば...。」
ご安心ください。
当事務所は人事労務の専門家です。
お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談はこちら
| 対応エリア | 茨城県/つくば市/土浦市/牛久市/龍ヶ崎市/常総市/かすみがうら市/石岡市/守谷市/筑西市/水戸市/ひたちなか市/笠間市/板東市/稲敷市/日立市/結城市/桜川市/高萩市/北茨城市/常陸太田市/常陸大宮市/鉾田市/行方市/潮来市 |
|---|
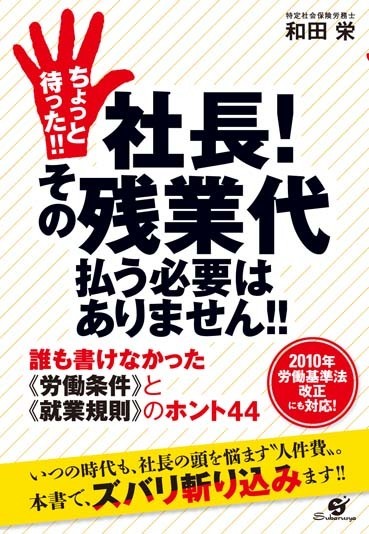
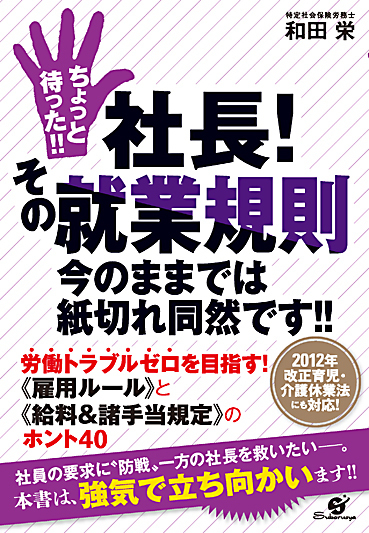
著書ご紹介
全国の書店で好評発売中!
【読者プレゼント】
書籍のページ数の関係で割愛した10項目を番外編としてプレゼントいたします。ご希望の方は、以下に必要事項をご入力のうえ、送信してください。